『ADHDでよかった』(立入勝義著)のタイトルに、「ADHDで”なにが”よかったのか」を知りたくて夢中で読みました。
この本は34歳でADHDの診断をされた著者が、それまでの失敗経験と診断後の劇的に上手くいくようになった人生を総合して振り返り、「ADHDという発達障害は克服できる」と確信、「ADHDを抱える全ての人は成功できる可能性を秘めている」と断言しています。
なぜそう言い切れるのか、どうすればそう思えるような人生を迎えることができるのか、この2点に注目して『ADHDでよかった』をまとめます。
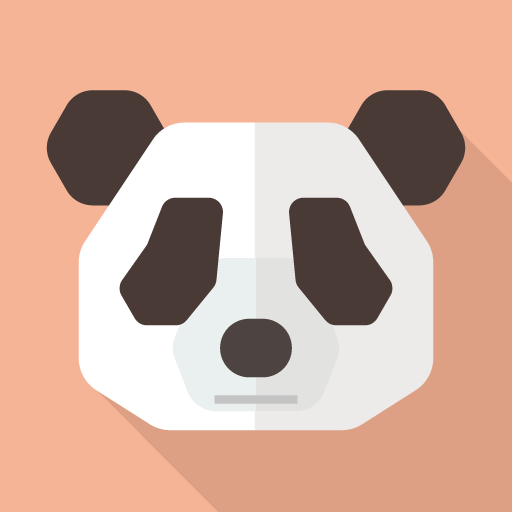
コノ本ヲ 読ンデホシイノハ コンナ人☟
・自分や家族、親しい人がADHDで悩んでいる人
・子供がADHDだと診断された人
・もしかしてADHDかもしれないと不安に思っている人
この本の3つのポイント
著者の実体験にもとづき「ADHDでよかった」と言い切っている
「ADHDだから大変」「ADHDとはこう付き合うとよい」という、一般的に後ろ向きな前提で始まるアドバイスが多いなか、この本で著者はこう言い切っています。
今ではADHDという発達障害は克服できると確信するに至りました。そう、ADHDを抱えるすべての人は成功できる可能性を秘めているのです。
立入勝義(2017)『ADHDでよかった』新潮新書p8

「ADHDにはスーパーパワーがあるから、明るい未来が開けているよ!」と全力で応援されているような気分になります。
薬物療法に前向きに取り組んだ経験を具体的に書いている
薬物療法と言われると、後ろ向きなイメージを持たれる方は多いのではないでしょうか。
でも著者は違います。
ADHDが先天性であれば、私は健常者の脳の状態を体験したことがないことになります。薬を飲んだらいったいどんな世界が開けるのだろうかと思いを巡らせました。
立入勝義(2017)『ADHDでよかった』新潮新書p21
薬に挑戦するというワクワク感が伝わってきます。
さらに、当時住んでいたアメリカでのカウンセリングや薬を服用した時の効果や副作用、かかる費用や依存性、そして薬をやめた理由にも触れています。

”薬を飲めば健常者の脳を体験できる”という考え方に「なんだかこの人いいな」と好印象をもちました。
「不注意」より問題な気質がある!
ADHDの三大気質として「不注意・多動性・衝動性」が挙げられます。
なかでもADHDの特性は一般的に「不注意」が問題視されますが、実際に問題なのは「過集中」のほうだというドクターの説明に、著者はしっくりきたようです。
「過集中の問題は、他に優先度(プライオリティ)が高く、本来なすべきことがあったとしても、そちらに気持ちを切り替えることができないことです。」
立入勝義(2017)『ADHDでよかった』新潮新書p22
ADHDの気質を理解する前は、物事の優先順位を守れないことで損をしたり、好奇心に任せていろいろ手を出した結果中途半端に終わったり、本来出せるはずの結果がだせなかったり時間やお金を無駄にしたりと、数々の失敗体験をしています。
子供時代は周りの人が管理してくれるためさほど問題になりませんが、社会人になると面倒を見てくれる人がいなくなる為、優先順位を狂わせる「過集中」は「不注意」より問題なのです。

管理してくれる人がいなくなった時、「過集中」は優先順位を狂わせ、幸せな社会生活や目指す目標から遠ざける可能性があるということを知っておく必要があります。
▽プロフィール
立入勝義(たちいり かつよし)
1974年大阪府生まれ。アメリカ在住。企業開発コンサルタント・プロデューサー・作家。世界銀行やウォルトディズニーでも勤務経験あり。
カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)地理/環境学部卒。
34歳で発達障害ADHDと診断。
どうすればADHDを克服できる!?
ADHDの克服方法として著者は下記を挙げています。
・自己を客観的に分析し課題を知る
・課題を乗り越える手段をいくつかもつ
・ADHDを受け入れる
まず、徹底邸に自分を客観的に分析し課題を知り、その課題に対して乗り越える手段をもちます。
課題を乗り越える手段のひとつが薬物療法です。
その他、例えば気分が落ち着かない・集中できない時には散歩と掃除をすすめています。
体を動かすことが好きなADHDの気質を利用して、散歩は最高の気分転換になるようです。
散歩をすることで脳が刺激されアイデアが浮かびやすくなるほか、太陽光を浴びることで幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を促し自律神経を整えることができます。

集中できなくなったら机にしがみつくのではなく、散歩をしたほうが効率が上がるそうです。体を動かすことで気持ちを落ち着かせて集中力を高める作戦です。
また掃除は作業後、すぐに効果が実感できすがすがしい気分になれること、調子が悪いときはカバンや財布の中身がぐちゃぐちゃになりがちなので、そこも整えることで気持ちを落ち着かせ集中力が高まることも。

気分転換ばかりしていると仕事が捗らず焦りがでてくるかもしれないけど、そこは過集中がカバーしてくれるから大丈夫なんだそうです。
また、不注意については、モノをなくさないために愛着のあるものだけを持つ・スマホで一括管理すればモノが減らせる、というアドバイスも。
優先順位を意識する方法としてもスマホを利用し、メモ機能などにウイッシュリストを作成し、定期的に追加削除見直しを加え、優先順位を常に意識して生活できるよう工夫できるそうです。
著者はADHDの診断をされたことがきっかけでADHDである自分を受け入れて変身(覚醒)できた、と言っています。
人生が公私ともに上手くいっていないことを勇気をもって受け入れ、自分を変える努力をし、成果がでなければ成果・生産性第一としてプロセスを変えてみる。
さらに自分の武器を知り磨き上げることで、様々な仕事で成功を収めています。
弱点を補強することも確かに大事なのですが、それ以上に大事なのは自分の武器を磨き上げることです。自分の課題に向かいあう一方、自分は何が一番得意なのかを徹底的に考えました。
立入勝義(2017)『ADHDでよかった』新潮新書p140
ADHDの秘められた能力!
NYのある教授が、退屈や決められたことを嫌い、好奇心旺盛な気質のADHDには定住型の現代社会には向かないけど、狩猟や遊牧をしていた原始時代では成功者だったのでは、と言っています。
実際に、「思いついたら吉日」を常に実行しているADHDの衝動性気質は、言い換えれば実行力に優れています。
興味のあることに「過集中」すれば、情熱を傾け黙々と努力することができます。
「多動性」は体内に有り余るほどのエネルギーがあるということになり、そのエネルギーを吐き出すように練習を重ねたADHDの有名トップアスリートも数多く存在します。
その秘められた能力を伸ばすためには、「よき理解者」が必要で、よいところに注目して支援してくれる人がいるとよいとされています。

もし子供がADHDなら保護者が一番の「よき理解者」でありたいところです。
さらに面白い研究結果が示されていました。
ADHDの人は「報酬」に対する反応が健常者と違うというのです。
ADHDの人は行動直後に報酬がでると健常者より満足度が高いのですが、時間が経つとともに健常者に比べ短い時間で急降下しています。

子供がほめてほしいテンションが高い時にほめるとすごく喜ぶのに、タイミングがずれると反応が薄いのは特性のせいなんですね。
子供が「テストでいい点とれた!」と嬉しそうに見せてくれた時=ほめてほしい時だから、そのタイミングを逃してはいけないということですね。
この報酬に対する反応も活かして、子供たちの良い点に注目して支援することができれば、子供たちの能力をもっと伸ばしてあげることができそうです。
まとめ
『ADHDでよかった』を読んだレビューをまとめました。
この本は「子育てのヒントに」と手に取ったのですが、自分自身に当てはまることが多すぎて、読み終わった今、一度私もカウンセリングを受けてみようかなと思い始めています。
ADHDを克服するための客観的分析にカウンセリングを利用することも一つの手段だと気付いたからです。
ADHDを克服するには自分の課題を知り、乗り越える手段をもつこと、そして成功するにはそんな自分を受け入れる(子供ならよき理解者になる)ということがわかりました。
自分自身にも子供たちにも今すぐ使えるネタを早速取り入れてみようと思っています。
この本には、ADHDの子供をもつ親のふるまいや、発達障害というマイノリティに対する社会整備にも言及しています。
多様性の時代、発達障害の捉え方もマイノリティとして社会に認められる手伝いが自分にもできないのかと新たな気付きももらいました。



コメント