発達障害とは何か、自閉スペクトラム症とは?
発達障害の特性をもつ子供の母として、知っておきたいことを簡単にまとめました。
知識があれば子供の気持ちがもっと理解できるはず。
子供の困りごとを解決したい時に参考にしていただければ幸いです。
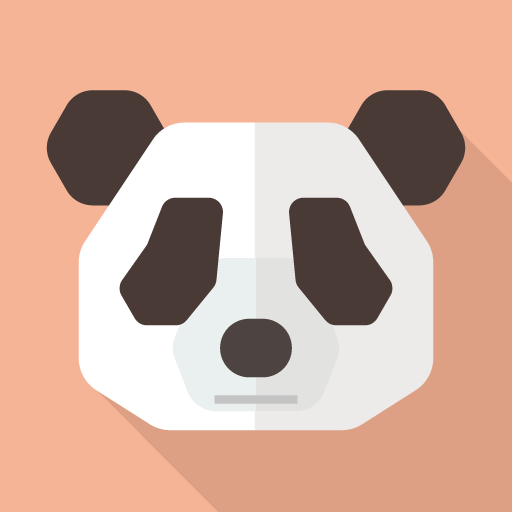
コノ記事デ ワカルコト
✓発達障害とは何か
✓自閉スペクトラム症とは?
✓自閉スペクトラム症の子供への接し方

基本的な知識ですが、私自身がすぐ忘れてしまうので忘れた時にすぐ確認できるようにまとめてみました。
発達障害とは何か簡単にまとめると
発達障害とは何か簡単にまとめたわかりやすいNHKのサイトを見つけました。
発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさ・凸凹(でこぼこ)によって、社会生活に困難が発生する障害のことです。
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/hattatsu/about_dd.html
発達障害の種類は主に3つあります。

これらは図のように、ASDのみの特性の人もいればASD×ADHD、ADHD×LDなど合わさった特性を持つ人など様々です。

長男も次男も保育園のときにASDと診断されましたが、ADHDとLDの傾向もあります。
自閉スペクトラム症(ASD)の特徴は?
自閉スペクトラム症(ASD)とはこだわりが強い・対人関係が苦手という特徴があります。
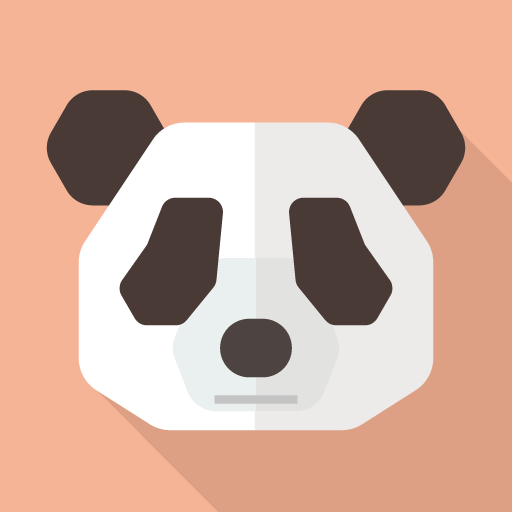
自閉スペクトラム症ノ特徴☟
・対人関係が苦手
・こだわりが強い
自閉スペクトラム症は子供の20~50人にひとり、男性に多く女性の2~4倍と言われています。
自閉スペクトラム症(自閉症スペクトラム障害)は、自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障害などの総称。これらは共通した特性があるため別々の障害ではなく虹のように一つの集合体として捉えようという考え方。

「自閉スペクトラム症」と呼ばれる前は「自閉症」「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害」と呼ばれていたそうです。長男は最初「広汎性発達障害」と診断されました。
自閉スペクトラム症(ASD)の子供の特徴
自閉スペクトラム症の特徴である「対人関係の苦手さ・こだわりの強さ」のせいで集団生活において苦労が絶えません。
子供が小さいうちは、この特徴をまわりの大人がいち早く理解しサポートすることが大切だと言われています。
例えば、「対人関係の苦手さ」の特徴的な行動は
・表情や視線、話しぶりから相手の気持ちを理解することが難しい(空気が読めない)
・孤立・受け身すぎ・一方的すぎなど双方向のコミュニケーションが難しい
・自分の好きな話には饒舌になりすぎる
・普通に話していても相手を不快にさせてしまう
・妙に大人っぽい不自然な言葉遣いをする

人に関心が弱く、相手の気持ちや状況などあいまいなことを理解するのが苦手です。事実に基づく行動をしたり、臨機応変に行動出来ないため誤解されがち。
「こだわりの強さ」の特徴的な行動は
・特定のものごとに強い興味や情熱をもつ(その興味の範囲は狭い)
・興味のあることは優秀な結果を出す反面、興味がないことはほとんど手を付けない
・競争・順番で1番になれないとパニックやトラブルになる
・ゲーム・アニメ・インターネットなどに没頭する
・スケジュール管理が出来ない
・ひとつのことに集中しすぎてまわりがみえなくなる

好き嫌いが極端で、自分のやり方やペースを最優先したい傾向が強く、興味のないことは苦手だが興味が強いことは良い結果が出やすい。
そのほか「感覚のかたより」や「体の動かし方が不器用」な特徴がある子もいます。

長男は手先が超絶不器用&触覚過敏でマスクがつけられず、次男は聴覚過敏で大きな音などが苦手です。
自閉スペクトラム症(ASD)の子供への接し方は?
「自閉スペクトラム症」なんて難しい名前に、「接し方なんて…」不安に思う方も多いかもしれませんが、出来る事を少しずつ生活に取り入れてみてください。
ここでは我が家で実践している(過去実践していたことも含め)接し方を紹介します。
・子供の得意なこと・苦手なことを理解し、得意を伸ばすよう環境を整える

長男は手先が超絶不器用でしたがお絵かきが好きだったので、保育園と家庭ではお絵描き帳とクレパスを欠かさないようにしたことで楽しく手先を動かす練習ができました。また恐竜と宇宙に興味が強かったので、それぞれの図鑑を5~6冊持っています。
出来ない事が多い分、得意なことで出来る事を意識的に増やすと成功体験も増え自信につながります。
・出来ない事は自分で「出来ない」と伝えることができるよう促す

長男の場合書字が苦手で板書が難しいので、担任の先生と事前に板書についてのルール決めをしています。今は集中できない時は「集中するために本を読んでよいか」と許可を取る練習中ですが、なかなか言えていないようです。
・ルールを具体的に説明する・ルールを可視化して示す
彼らは暗黙ルールは理解できません。
他の子なら自然に理解できるルールでもそれをくみ取ることが出来ないので、気付いた都度「そのルールがなぜ必要なのか・どう行動すべきなのか」を説明します。
理解が薄い場合は、目につく場所に箇条書きして張り出すことで、いつか理解してくれると信じています。

小学校には意外に暗黙のルールが多いので、学校で出来ていない集団生活や困りごとを定期的に担任の先生に確認し、ルールを具体的に説明しています。
・朝の準備・帰宅後の片付けを可視化
スケジュール管理が苦手、先の見通しを立てるのが苦手なので、毎日の朝夕のルーティンがなかなか習慣化しません。
毎日同じことを言うとイライラして無駄に怒ってしまうのを避けるためにも朝夕のルーティン表を【やること順に完結な文字で】作りました。

①トイレに行く②手と顔を洗う③着替えをする④ごはんを食べる…など朝の準備を順番に紙に書いて目立つ場所に置いていました。イラストで描いたり、マグネットでカードを作り出来たらひっくり返す、というボードを作っていたお母さんもいました。
・マスクがつけられないかわりになるものを用意
感覚過敏でマスクがつけられない為、学校に理解を求め代用になるものを探しました。

片付けの苦手さのサポートがしたいのですが、私も片付けが苦手…。サポート出来ていないこともたくさんあります。
まとめ
すごく不安だった時、子供の主治医から「得意を伸ばせば苦手はあとからついてくるから大丈夫」と言ってもらったことがあります。
苦手を克服させるのは大変だけど、得意を伸ばしてあげるのは楽しいことです。
主治医とのこの会話のおかげで、出来ない事ばかり気にせず「楽しいことに向かってサポートしていけばいいのかな」と気持ちを切り替えることができました。
発達障害という言葉は今でも好きではありませんが、普通の人とは脳の働きが違う子供たちはたくさんの可能性を秘めた存在だと思っています。

特定のことにこだわりをもって突き進んでいく彼らは天才にしか見えません。
そんな秘めた可能性を引き出す楽しみのある子育てを経験できて幸せです。

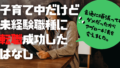

コメント