発達障害の子供への接し方について超絶わかりやすいおすすめ本をご紹介します。
”発達障害の子供を伸ばす”本として作られていますが、発達障害ではない子供たちにも使える”魔法の声かけ”方法が盛りだくさんです。
忙しいママさんも読める、一目でわかる工夫もされているので頑張らずに理解でき、実践できて使いやすい1冊。
子育てに悩んでいる方必見です!
この記事では、私が子供への声かけや接し方に迷ったときに眺めていた本『発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ』についてまとめます。
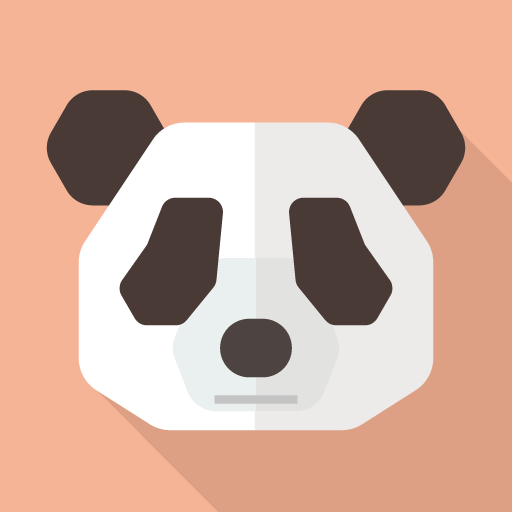
コンナ人ニ 読ンデ ホシイ
✓発達障害の子供を伸ばす接し方・声かけ方法の本の購入を検討している人
✓子供を叱りすぎる→自己嫌悪→また叱る…の負のスパイラルから抜け出したい人
✓病院や療育センターのペアトレでは物足りない人
✓前向きな気持ちで子供に向き合えるツールが欲しい人
✓発達障害の子供を理解する材料がほしい人

頑張って読まなくても一目見ればだいたい理解できるから、すぐ実践できます。今でも私のお助け本です。
この本の3つのポイント!
4コマ漫画でわかりやすい!
この本の一番好きなところは、一目で状況を把握→実践できるよう構成されているところです。

忙しいときに本なんて読む暇ないですよね。特に療育の本は読むべきかもだけど難しそうで読みたくない…。
でもこの本は、忙しい日でもパラッとページさえめくれば4コマが目に入ります。
NGな接し方と良い接し方の例が4コマ漫画で比較できるようになっているので見開きの比較漫画さえ見ればだいたいわかる!

「悪い例、そのまま私…(-_-;)→じゃあどうすればいい?」が一目で理解できるからすぐ使えるんです!
漫画の周りに詳細が文章で説明されているので、余裕があるときに文章を読む、というスタンスでも大丈夫な本です。

子供を怒りすぎて自己嫌悪な時にパラッとめくれば、前向きになれるヒントをもらえます。
基本的な療育方法が理解できる!
療育センターや病院などの専門機関で療育やペアトレをしてもらっても、その時はわかっている気でも帰ったらわからなくなった…なんてことありませんか?
この本には療育の基本的な考え方がわかりやすく説明されています。
なぜほめることが大切なのか、スモールステップって何のために必要なのか、よい親子関係を築く理由など療育では当たり前とされている基本知識が簡単な言葉で示されています。

専門医や療育センターの先生から「やったほうがいいよ」と言われてやってたけど、その理由が理解できれば言われたこと以上のことが出来るようになります。
基本的なことは最初に教えてもらうはずですが、最初は知らない言葉ばかりで全く頭に入りません。
ある程度子供の特性を理解してからこの本を読むと、取り組んでいる療育の理解が深まります。

でもやっぱり難しくてすぐ忘れるので、私は忘れたころになんとなく眺めて思い出してます。
とにかく具体的ですぐ使える!
この本は自閉症のお子さんを育てられたお母さんが、効果のあった声かけ方法をまとめられています。
なので、日常のあるあるな事例ばかり。
手を洗う時の声掛け、お片付けの時の指示の出し方、「早く」を言わないでよくなる声掛け方法、お茶をこぼした時の接し方、宿題などやるべきことをやらせる声掛け方法などたくさんの事例について、「私の声掛けで子供はどう思うのか」まで理解できるので、実践につながりやすいと思います。

この方法をうまく使えば、子供も自分も気分よく過ごせる時間が増えますよ。
ほめるコツ!
いざほめようと思っても、何をほめてよいのかわからないことってありますよね。
子供ができなかったことができるようになったり、特別なことをしたときだけほめるのではなく、実は日常にほめるチャンスはたくさん転がっています。
実は子供が当たり前の行動をしている時こそほめるチャンスです!
例えば、食事の時に子供の姿勢が気になったら
【NG例】
「姿勢を伸ばして」と注意→子供が姿勢を伸ばす→数分後姿勢が崩れる→「ほら、また姿勢が悪い!」→子供が姿勢を正す→また崩れる→「何度言ったらわかるの⁉」

出来ないところばかり目について、だんだんイライラした口調になってしまいます。
【GOOD例】
「姿勢を伸ばして」と注意→子供が姿勢を伸ばす→「そう、それでいいよ」とほめる→30秒後ごろまだよい姿勢をしていたら→「姿勢いいね!頑張ってるね」→数分後姿勢が保たれていたら→「姿勢よくてかっこいいよ!」
【GOOD例】のように、こんなチャンスなら日常にゴロゴロありますよね。
指摘して出来たこと、その後も出来ていることにフォーカスをあてると、いくらでもほめるネタはあるんです。
ほめている時は俳優になったつもりでテンションを高め、周りから親バカと思われても気にせず、笑顔でほめちぎりましょう。
shizu著 平岩幹男監修(2013)『発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ』講談社p52

私は起こされて起きた子供たちに毎朝「起きれたね!頑張ったね!」とほめています。当たり前のことが出来ているだけですが、ほめている私も気分がよくなります。
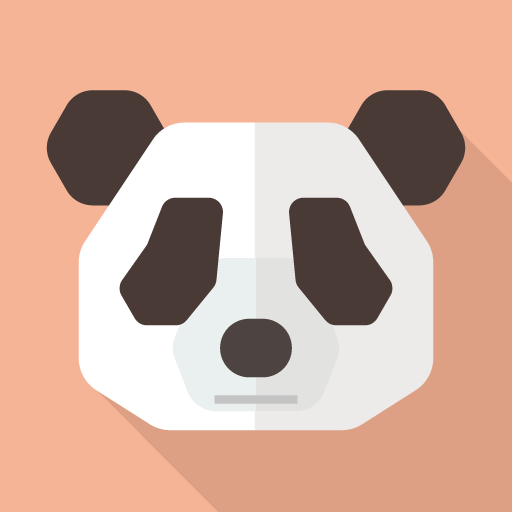
「ほめるコツ」アドバイス
・1回叱ったら3回ほめて!
・ほめ言葉を動作で補強!
→頭をなでる・笑顔で頷く・ハイタッチ・抱きしめるなどをほめ言葉にプラス♡
・ほめ言葉を台無しにするNGワード
→他人と比較・ほめ言葉のあとの次の課題の提示・ほめ言葉のあとの嫌味

「縄跳び10回飛べたんだね!次は20回が目標だね!」「頑張ったね。でもこれくらい出来て当たり前だけどね。」「大根食べれたね!でも○○くんはピーマン食べれるらしいよ。」これは全てNGワードです。
指示の出し方!
子供たちに指示を出すとき、思っている以上に命令口調になってしまうのは私だけでしょうか?

「走らないで!」「早くして!」「○○しないで!」ばかり言っている気がします…。
この本を参考に私が実践している指示の出し方を3つご紹介します。
肯定的な言葉をかける
子供に注意するとき、指示を出すとき、肯定的な言葉かけをするよう心がけています。
例えば☟
走らないで!→歩きましょう
片付けないとおやつはあげないよ→片付けたらおやつ食べようね
うるさい!→2の声で話してね(声の大きさを1~5の数字で教えています)
お茶こぼさないで→コップを両手で持って飲んでね

肯定的な言い方は、自分のイライラ軽減効果もあります(笑)
子供の近くで指示をだす
夕食前、子供がテーブルにおもちゃをぶちまけている時、食事の準備をしながら「テーブルの上のおもちゃを片付けて」と声をかけることあると思います。
キッチンで自分の手を動かしながらリビングの子供たちに指示を出しても…全く言うことを聞いてくれませんよね。
これは子供たちが言うことを聞かないのではなく私の指示の出し方が悪かったことに、この本を読んで気付かされました。

キッチンからリビングにいる子供たちに「片付けなさい!」と大声で指示をしていましたが、全然言うことを聞いてくれずイライラしていました。でも実は自分の指示の出し方が悪かったなんて衝撃でした。
夕食前にテーブルを片付けてほしい時、”一旦自分の作業を中断して、子供のそばに行き自分に注目させてから指示を出す”ようにすると…すんなり子供が片付け始めてくれるんです。

自分の作業を中断する時間は30秒くらい。たったそれだけのことでスムーズに指示が通るようになります。
ポイントは子供のそばに行き、自分に注目させてから伝えること。
目を合わせて伝えるのも効果的です。
急がせたい時はカウントダウン!
急いでいるとき、つい「早くしてー!」と急ぐ素振りのない子供にイラつくことありませんか?
そんな時はカウントダウンが有効です。
例えば、朝の着替えのとき、

パジャマが10秒で脱げるかな!?

できるー!

じゃあいくよ!よーいドン!10,9,8,7…

できた!

おぉー出来たね!次はズボン!10秒で履けるかな?
みたいなやり取りをすると手間はかかりますが、時間は短縮できお互い気分よく物事が進みます。
また、子供が宿題をなかなか始めない時、何時から宿題を始めるのかを子供に決めさせ、タイマーをかけて時間を意識させると上手くいくことが多いのでオススメです。
まとめ
おすすめの本『発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ』についてご紹介しました。
何気なく発している言葉を意識して改善することは、簡単そうに見えて実は結構大変です。
実は私も常に出来ているかと言われると…出来ていない事も多々あり子供の反応をみてハッとします。
でもそれでいいのかな、とも思っています。
いつもいつも教科書通りに頑張ることはできませんが、「今度はこう伝えよう」と意識することで私も成長できているはず。

そう思って頑張りすぎず頑張ってます。
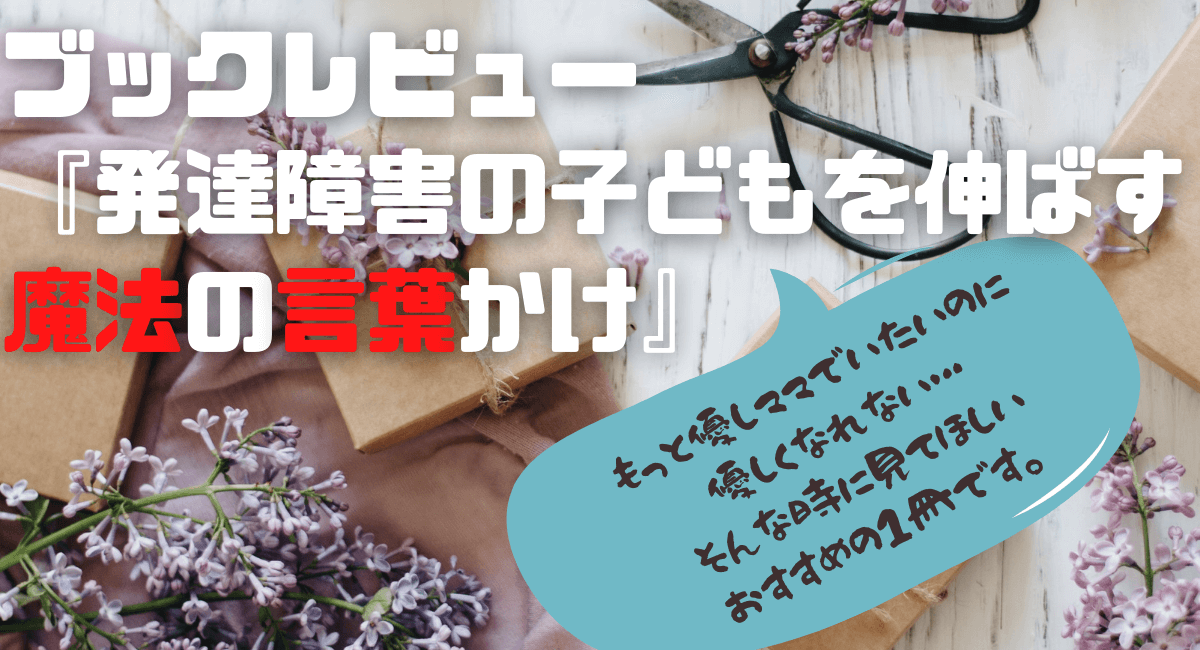

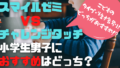
コメント