頑張りすぎる子供に有休をあげることにしました。
ここでいう有休とは、学校を休んでもよいとする日のことで家庭内のルールです。

我が家では月に1回、学校を休みたかったら休んでもよい日を設けています。
この記事では、なぜ我が家で有休制度を作ることにしたのか、また有休が必要な理由についてまとめます。
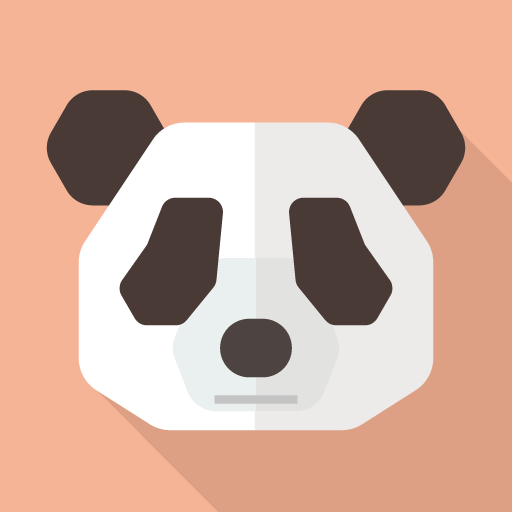
コノ記事デ ワカルコト
✓我が家が有給制度を取り入れた理由
✓我が家の有休のとり方のルール
✓頑張りすぎる子供に有休が必要な理由
✓有休が必要な子供のタイプ
我が家が有休制度を導入した理由
小学生の次男はグレー寄りの発達障害の特性があります。
集団のなかでは”おりこう”に振舞うので、パッと見では成長の遅れはわかりにくいタイプですが、”過剰適応”してしまい、必要以上に空気を読んで周りに合わせてしまいます。
ということで、必要以上に疲れて帰ってきます。
本人は頑張りすぎていると自覚がないので、それを自分でケアすることもできません。

そんな状態が続くといつか動けなくなってしまうので、その前に逃げ場を作りました。
その逃げ場が”月に1回学校を休んでよい”有休制度です。
【有休制度を導入した理由】
・頑張りすぎる子供の頑張りすぎを防止するため
・疲れた時の一時的な逃げ場を確保するため
我が家の有休取得のルール
我が家は共働き家庭の為、急に「明日休む」と言われても困ってしまう、と本人家庭の事情を理解してもらい、有休を取得したいときは2~3日前までに休みたい日を申告してほしい、と話しています。
また運動会や発表会シーズンになると、頑張らなくてはいけない集団活動が増え、いつもに増して疲れがたまるので、その月にはもう1日増やすことも可能だと事前に伝えています。

コロナ以降集団活動が減り、彼らの苦手な時間が減っています。
【有休取得のためのルール】
・月1日(イベント月は2日)まで取得可能
・2~3日前までに申告すること
有休が必要なタイプとサイン
有休が必要なタイプは、とにかく頑張りすぎてしまうタイプの子供です。
発達障害の特性のある子は、何かしら発達の遅れや凸凹があり、日々の暮らしに困りごとがあります。
困りごとを気付いているかどうかは人それぞれですが、無意識に頑張りすぎている子が大半です。
また、真面目なタイプや気が利く子も頑張りすぎている可能性があります。
そんな子供たちは有休というお守りがあると、幾分か気持ちが楽になるのでは、と考えています。
【私が考える有休が必要なタイプ】
・発達系で無意識に頑張りすぎている子供
・真面目なタイプの子供
・気が利く子供
普通に学校に行っていても実は頑張りすぎているサインを出している場合があります。
例えば
【頑張りすぎのサイン】
・いつもよりイライラしている
・寝つきが悪い
・落ち着きがない
・家で話をしなくなった
他にも子供によって変化は違うと思いますが、小さなサインを出しているかもしれません。
そんな時は有休制度を伝えてみてはいかがでしょうか。

次男の場合、体の落書きが頑張りすぎのサイン。学校で手のひらや甲にマッキーペンで落書きをしてくるようになります。
まとめ
頑張りすぎる子供に有休制度を導入したその理由と詳細をまとめました。
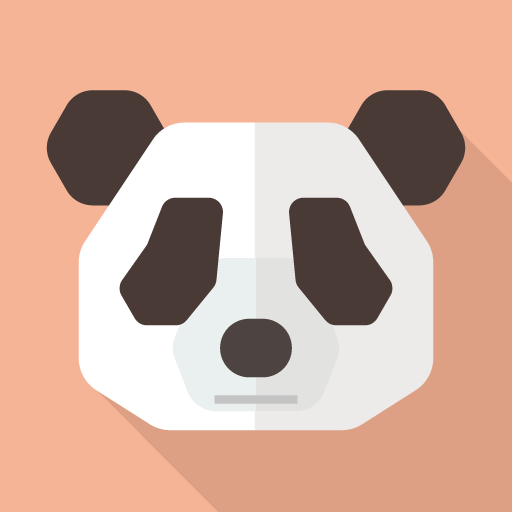
コノ記事ノ マトメ
・有休を導入した理由
→頑張りすぎを防止するため
・ここでいう有休とは
→月に1日学校を休んでよい家庭内ルール
・有休取得のルール
→3日前までに申告が必要
・有休が必要なタイプ
→無意識に頑張りすぎている子
頑張りすぎが積み重なって不登校や自傷行為につながる可能性もあるので、特に過剰適応タイプの次男は気を付けるように、と主治医に教えてもらってから、我が家では有休制度を導入しました。
有休について息子に伝えて半年がたちましたが、まだ1度も申請されたことがありません。
疲れている時は私から「有休どうですか?」と声をかけることもありますが、「まだ大丈夫」と言われます。

子供って思っていた以上に真面目。有休をズル休みだと認識しているのかもしれません。
そんな時は、放課後等デイサービスをお休みして学校が終わったら直接帰れる日を増やしたり、一緒にお風呂に入ったり(最近は拒否されますが涙)、ボードゲームの時間を作ったり、一緒にいる時間を増やすようにしています。
それでリラックスできているのか、本人でないとわかりませんが、特に体の落書きがひどくなったときは注意して様子を見るようにしています。
コロナ禍でオンライン授業も主流になってきたので、有休制度よりオンライン授業のほうがちょっとした逃げ場にはちょうどいいのかもしれません。
最後にくれぐれも誤解しないでほしいのですが、子供の有休制度は勝手に作ったもので、学校がよいとしたものではありませんので、ご注意ください。

子供の心の健康のために勝手に取り入れてやってます。
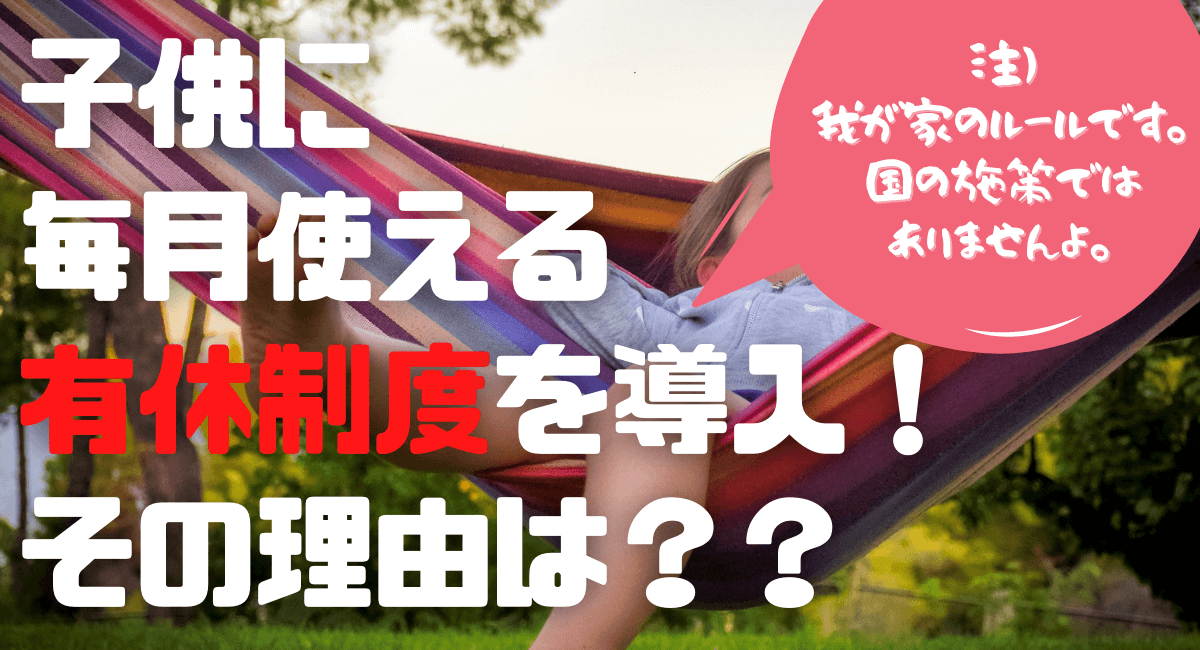


コメント