発達障害の子供を通わせるなら保育園と幼稚園どっちを選ぶのか、共働きの家庭なら迷うところです。
ちょっとだけ成長の遅れが気になる程度のグレーゾーンの子だったどっちがいいのか…?
実際、保育園と幼稚園はどっちが発達障害の子供たちを受け入れる環境にあるのでしょうか?

大切な子供を預かってもらう場所だからいい方を選びたいですよね!
そこで、現役保育士さんで幼稚園で勤務経験のある方にインタビューを実施し、現場の状況についてぶっちゃけトークをしてもらいました!
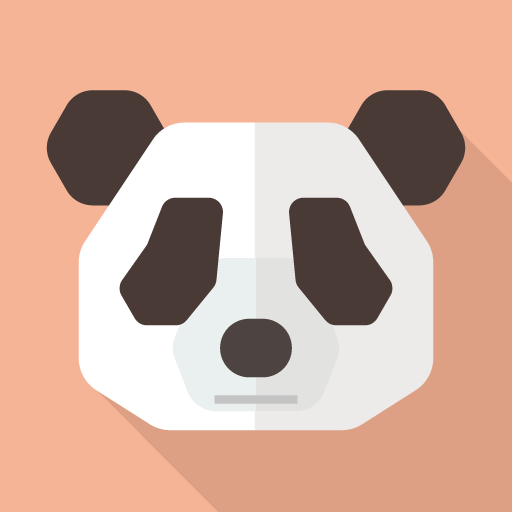
コノ記事デ ワカルコト
✓保育園と幼稚園の発達障害受け入れ態勢
✓保育園と幼稚園の先生の考え方の違い
✓私たちが子供のために出来る事
保育園・幼稚園の発達障害児受け入れ態勢は?現役保育士マユコさんに聞いてみた!
現役保育士マユコさんってどんな人?
今回インタビューを快く引き受けていただいた現役保育士マユコさんのプロフィールはこちら☟
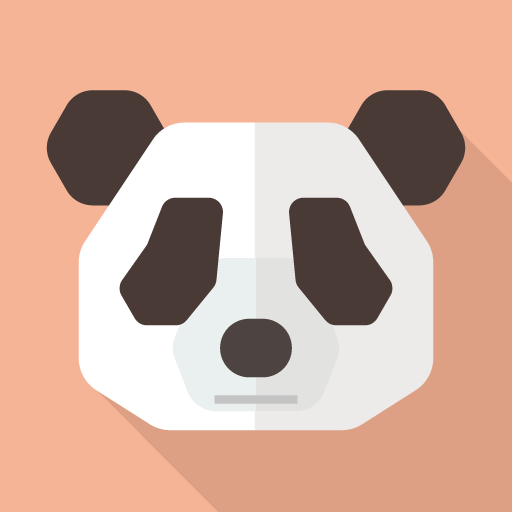
現役保育士マユコ サン ノ プロフィール
・出身地:埼玉県
・経歴:児童養護施設・保育園・幼稚園・インターナショナルキンダーガーデン・学童保育で先生をされた経験豊富な方です
・趣味:読書・太極拳

2人のお子さんをもつお母さんです。
マユコさんは保育園や幼稚園だけでなく、児童養護施設や学童保育などの経験もある超ベテラン先生です。
保育園・幼稚園の現場の状況は?

マユコさんよろしくお願いします。早速ですが、保育園と幼稚園の発達障害児の受け入れ態勢の違いがあれば教えてください。
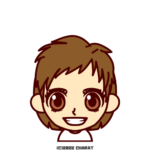
まず保育園と幼稚園の違いってわかりますか?

たしか管轄が違うんですよね?
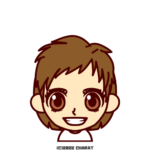
そうです。保育園は児童福祉法に基づく児童福祉施設で厚生労働省の管轄、幼稚園は教育基本法に基づく教育施設で文部科学省の管轄です。それぞれ法令や管轄が違うので保護者が預ける目的が異なります。
| 保育園 | 幼稚園 | |
|---|---|---|
| 目的 | 保育に欠ける家庭の代わりに 保育を行う施設 | 生活習慣や集団活動のルールを 学ぶ教育機関 |
| 対象年齢 | 0歳~小学校入学前 | 3歳の春~小学校入学前 |
| 標準保育時間 | 8時間 | 4時間 |
| 先生の必要免許 | 保育士 | 幼稚園教諭 |
| 管轄 | 厚生労働省 | 文部科学省 |
| 根拠法令 | 児童福祉法 | 教育基本法 |

保育園は子供のお世話をしてくれる場所で、幼稚園は勉強する場所なんですね。
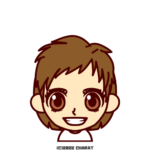
施設で異なることもありますが、大枠はそうですね。先生のタイプも違うんですよ。どちらかというと保育園の先生はおせっかいなくらい子供や保護者に関わろうとする先生が多いように感じます。

なんかわかる気します!先生というより、気のいい親戚のおばちゃんみたいな気さくな人多いですよね。
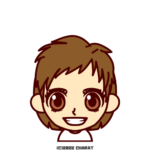
だから発達の遅れが気になったら言わずにいれないというか、見過ごすことができないというか。幼稚園の先生は1人の先生に対して35人の子供を指導するうえ子供と関わる時間が短いので、集団行動が出来ない子をすべて面倒みることが難しいんです。

小学校に入ってなんとなく思ってたんですが、この子発達系かなって思っても療育を受けていなかったり、その必要性に気付いていない人が幼稚園出身の子って多いなって。もちろん幼稚園や先生によると思いますが、保育園ほど幼稚園の先生はグレーの子たちに関わることがないんですね。
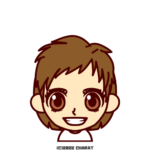
保育園も幼稚園も一定時間の発達障害の研修があるので知識はあります。発達支援の専門家を育てるには知識と経験が必要なのですが、実際現場にはお手本となる人がほとんどいないんです。本当は専門家でありたいのですが、人手不足で。実践したくても人員配置は戦後から変わっていないので、特別な発達支援まで手がまわってないのが現状です。重労働低賃金なのもあって、いろんな理想と現実の葛藤でやめていく先生も多いんですよ。

目の前にどうにかしてあげたい子供がいるのに、人手不足でどうにもできないなんて、聞いてるだけでツライです。私たち保護者ができることってありますか?
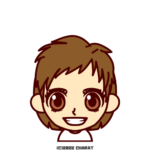
保育園や幼稚園の環境を改善してくれそうな議員さんに選挙で投票するのは大切だと思います。今すぐできることは、もしお子さんの発達の遅れが少しでも気になるようなら集団生活の様子を見に行ってください。そこで違和感を感じたら専門機関へ相談されることをおすすめします。自治体の専門機関と保育園・幼稚園そして保護者が必要とみなせば、補助金がでるので追加で保育士を雇い手厚い対応ができるようになります。

発達の遅れを指摘されるのを待つのではなく、気になることがあれば集団生活の実際の様子を見に行っていいんですね。迷惑になるかと思って参観日以外見たことなかったけど、普段みえない集団活動を知ることは大切ですよね。根本的な改善としては、行政に変わってもらうために選挙の投票は必須ということですね。
まとめ
10人に1人が発達障害と言われている現在、専門家でない限り軽度なら特に発達の遅れを幼児期に家庭で気付くのは難しいはずです。
グレーゾーンを含む発達障害の子供を保育園と幼稚園どっちに通わせるか・どっちが向いているか、を判断する材料のひとつにマユコさんのインタビューも参考にしていただけるのではないかと思います。
私は、保育園や幼稚園の先生も発達の専門家でありたいけど実際は人手不足でそこまで手がまわらない、という事実を知り驚きました。

息子たちは保育園で発達の遅れを指摘されましたが、気付いてもらえただけでもありがたいことだったんですね。
子供の発達の遅れを指摘された時すごくショックで驚きましたが、でも指摘される前から息子に対するちょっとした違和感をもっていました。

目があいにくいのは私がゆっくり話してあげてないせいかな、とか、他の子よりちょっと個性的だな、程度の違和感です。
この違和感を察知できれば保育園へ活動の様子を見に行って違和感の正体を探ることができたと思いますが、残念ながら私は指摘してもらうまでその必要性を理解できていませんでした。
子供が発達障害かも、と認めることはコワイし勇気がいる事ですが、本人が困っているのなら認めて支援を受けるべきだと私は思います。
集団の環境が成長を促すことができないのなら、環境を変える必要もあります。
それを見極めるのは保育園や幼稚園の先生だけでなく私たち保護者もである、ということをマユコさんのおかげで気付くことができました。

現場にいる先生によって感じ方は様々だと思います。今回はマユコさんの感じている現場の現状を知ることでよい勉強をさせてもらいました。根本的な改善のためにも選挙はしっかり選んで投票せねばと思いました。
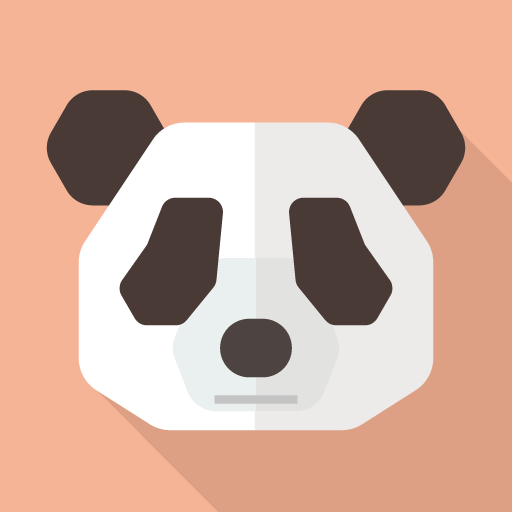
コノ記事ノ マトメ
・保育園・幼稚園の先生は発達の専門家ではないので任せっぱなしにしない
・子供に違和感を感じたら集団活動の様子を見に行ったほうがよい
・必要なら専門機関に受診し、専門家の意見を聞く
・必要なら加配保育をお願いする



コメント