作文や感想文、日記を書くのが大の苦手な息子たち、作文の書き方がわかりません。
作文の宿題が出る金曜日には家族でげっそり…。
金曜ロードショーが始まる頃にようやく夕食を食べはじめる、なんてしょっちゅうでした。

普通、学校の勉強だけで作文って書けるようになるものなの?
宿題が出るということは、困らない程度に教えられているはずですが…。

やる気はあるけど出来なくて、ホントに拗ねて泣いて大変でした(-_-;)
この記事では、作文が大の苦手だった長男に教えた作文の書き方と、苦手な作文の克服法についてご紹介します。
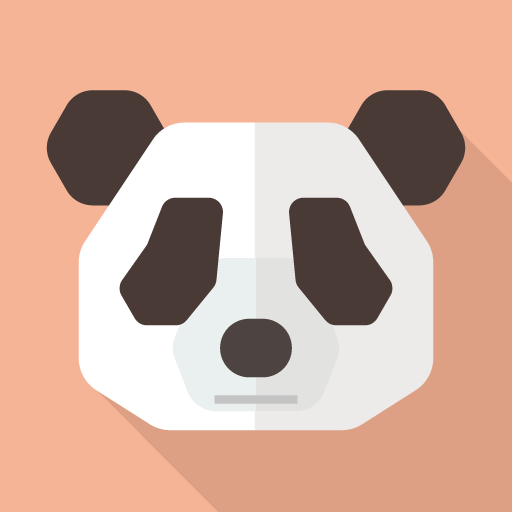
コノ記事デ ワカルコト
✓作文が苦手な子へ書き方を教える方法
✓苦手な作文を克服する方法

小学5年生になった長男、今でも作文は苦手だけど考え方はマスターしたみたい。今でも付箋を使った書き方で作文を書いています。
作文が苦手な子が作文が書けるようになるまで
まずは私が作文が苦手な長男に教えた作文の書き方を段階別にご紹介します!
1~2年生のころの作文の書き方!→苦手意識を和らげる

インタビュー方式で気分よく作文の構成を組み立て「出来た!」を積み重ねる作戦です。
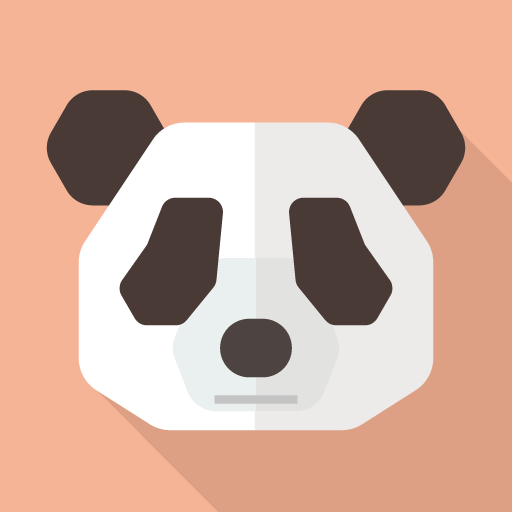
用意スルモノ→①ペン②大きめの付箋
「作文の宿題をしないといけない」と考えるだけで、憂鬱を通り越して涙が出ていた当時の長男。
まずは作文の苦手を和らげることに力を注ぎました。
やり方は以下の通りです。
【インタビュー方式で「出来た!」を積み重ねる作戦!】のやり方
①作文のテーマを事前にチェックしておく
②作文のテーマに沿って、子供にインタビューする

いつ、どこで、だれと、何をして、どう思ったか、を超ハイテンションでおもちゃのマイクを子供にむけてインタビューします。超ハイテンションがポイントです。
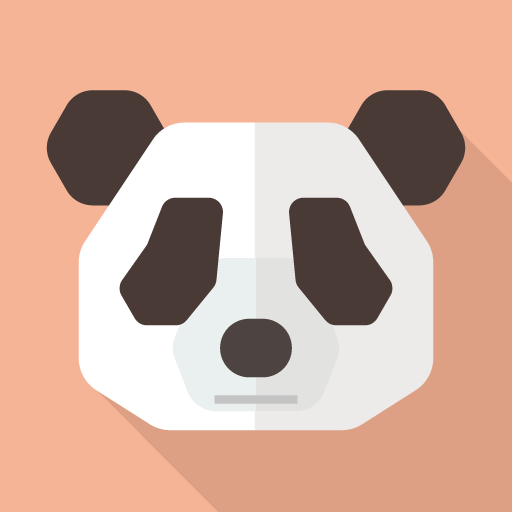
時間ト気持チ ニ 余裕ノアル 時二 実施シテクダサイ
③インタビュー内容を付箋に書く
④宿題のテーマを子供に伝える
⑤付箋を並べて、順番をバラバラにして一つずつ読み上げる
⑥宿題のテーマに沿う作文にするにはどの順番で付箋を並べるのがよいか一緒に考える。
※付箋を見ながら必要な助動詞「そして」「でも」「だから」などの付箋を用意
⑦付箋(助動詞も含め)並べる
⑧読んでみる
⑨「作文できたね!」と一緒に喜ぶ
⑩清書させる

「作文が出来た!」と思わせることが目的です。嫌々でも⑨でハイタッチしてみてください(笑)
清書させるのも一苦労するときがありますが、どうしても書けない時は、この作文はここまで清書して残りは付箋をはる、という強行突破をしたこともあります。

無理やりやらせて嫌な思いを残すより、出来たを優先したかったので、出来ない時は清書をあきらめていました。
3年生~の作文の書き方→一人で作文が書けるようになるために

項目ごとに付箋に書いて並び替える付箋で作文をつくる作戦!です。
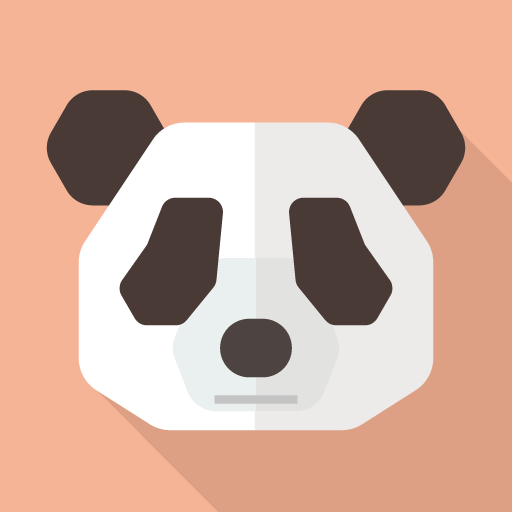
用意スルモノ→①ペン②「いつ・どこで・誰と・何を・どうした・どう思った」ト記入シタ6枚ノ付箋
【付箋を使って一人で作文をつくる書き方】
①事前に6枚の付箋(「いつ・どこで・誰と・なにを・どうした・どう思った」と記入したもの)を準備する
②付箋を一枚ずつ書く

書けない時はインタビューしながら引き出す
③書いた付箋を並べ替える
④並べて読んでみる
⑤必要なら助動詞を付け加える
⑥清書
読書感想文を書くときは付箋の内容を変える必要がありますが、付箋作戦でなんとか作文は書けます。
この方法は素晴らしい作文を作りたいのではなく、子供が自分で作文が書けるようになることが目的です。
一人でかけなかった作文をこの方法で克服し、一人で書けるようになりました。

拗ねて泣いて大変な思いをして作文を書いていた長男も、今ではなんとか作文の構成ができるようになり、作文を書くことを拒否しなくなりました。ただ自分の感情を表現するのが苦手なので、そこは今後の課題です。
まとめ
「作文が苦手な子へ書き方を教える」というテーマで、実際に作文が苦手な長男に教えた作文の書き方をご紹介しました。
苦手なことを無理矢理やらせるのと、少しずつ「出来た」という体験を繰り返すのでは後々の成果が変わってきます。
出来ない事を完璧にこなすのではなく、その子なりのゴールを設定し、そこまで出来たらOK!ということを積み重ねれば、少しずつできるようになると思います。

その場を完璧に仕上げてもその後上手くいかなくなることが多いし、やらせる親も辛くなってきます。
「いずれ出来るようになればいいから、今のゴールはココ」と本人も親も思えるならそれでいいのかな、と割り切れるようになってから気持ちが楽になりました。


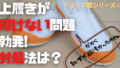

コメント